
展示会での名刺交換は、新たなビジネスチャンスを掴むための重要なステップです。
しかし、いざ会場に立つと「名刺交換のタイミングは?」といった疑問や、「そもそも展示会に名刺をいくつ持っていけばいいですか?」といった枚数に関する悩みが生じることもあります。
また、「渡す時、なんて言えばいいですか?」という基本的なやり方で戸惑う方も少なくありません。多くの来場者と接する中で、積極的な営業を受ける一方、中には怪しいと感じる相手もいて、正直名刺を渡したくないと思う場面もあるでしょう。
そんな時のスマートな断り方や、避けるべきNGな行為は?といったビジネスマナーも気になるところです。交換後のフォローメールまで含めた一連の流れを理解し、効果的な人脈形成につなげましょう。
- 展示会における名刺交換の正しいマナーと手順
- 名刺交換を切り出すべき最適なタイミング
- 名刺交換をスマートに断る方法と避けるべきNG行為
- 交換後の効果的なフォローアップと名刺活用術
失敗しない展示会 名刺交換の準備とマナー
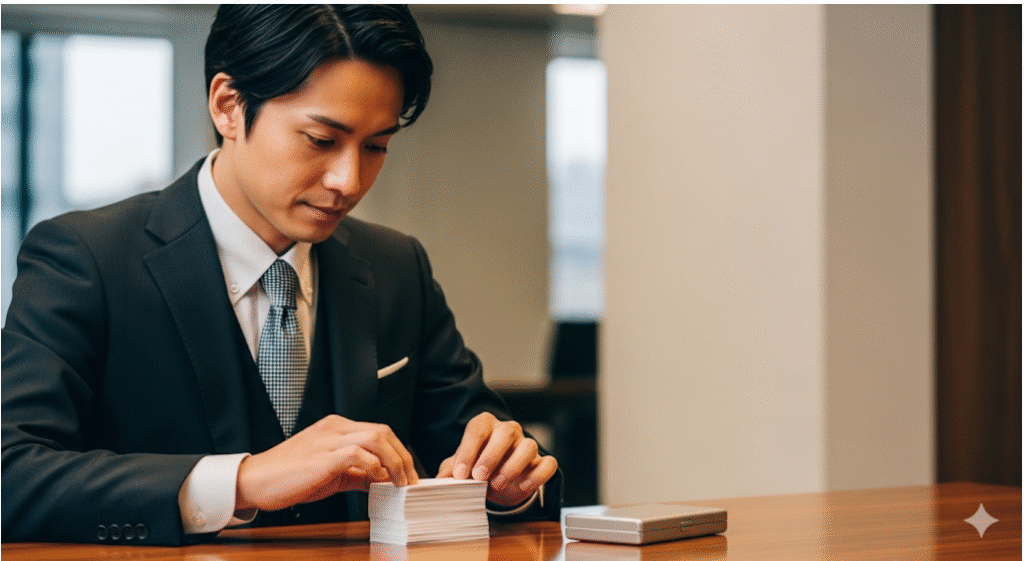
- 押さえておきたい名刺交換の基本マナー
- 正しい名刺交換のやり方を覚えよう
- 名刺を渡す時、なんて言えばいいですか?
- 準備すべき名刺の枚数の目安は?
- 展示会に名刺をいくつ持っていけばいいですか?
押さえておきたい名刺交換の基本マナー

展示会での名刺交換は、第一印象を決定づける重要な瞬間です。この数秒間のやり取りが、今後のビジネス関係を左右すると言っても過言ではありません。
基本的なビジネスマナーを徹底することが、将来の商談につながる信頼獲得の第一歩となります。相手に不快感や不信感を与えないよう、細部にまで気を配る必要があります。
服装と清潔感の徹底
まず、すべての基本となるのが身だしなみです。
人は見た目で相手を判断しないと言われますが、ビジネスの場、特に初対面の場では外見が与える影響は絶大です。
シワのないシャツやプレスされたジャケットを着用し、髪型や髭、爪の先まで手入れを行き届かせ、清潔感を保ちましょう。
ブースに立つスタッフ一人ひとりの印象が、そのまま企業のブランドイメージに直結します。
特に、ジェトロ(日本貿易振興機構)がまとめるような大規模な国際展示会では、国内外から多くのビジネスパーソンが訪れます。
その中で清潔感のないスタッフは、無意識のうちに来場者から避けられる傾向にあります。靴の汚れや磨耗なども意外と見られているポイントなので、事前に手入れをしておくことが望ましいです。
身だしなみチェックリスト
- スーツやジャケットにシワや汚れはないか?
- シャツの襟や袖は清潔か?
- 寝癖はなく、髪は整えられているか?
- 靴は磨かれているか?
- 爪は短く清潔に切られているか?
- 口臭や体臭のケアは万全か?
名刺入れの準備と状態確認
名刺交換の直前になって慌ててカバンの中を探すような行為は、相手を待たせてしまうだけでなく、準備不足で段取りが悪いという印象を与えてしまいます。
名刺はすぐに取り出せるよう、上着の内ポケットなど、定位置に専用の名刺入れを準備しておきましょう。
名刺入れの状態にも注意
使い古して角が擦り切れた名刺入れや、いただいた名刺でパンパンに膨れ上がった名刺入れは、相手にだらしない印象を与えかねません。
名刺は会社の顔であり、それを収納するアイテムも同様に重要です。本革製や金属製の落ち着いたデザインのものを選ぶと、信頼感を演出しやすくなります。
立ち振る舞いと表情
ブース内で腕組みをしたり、背中を丸めてスマートフォンを操作したり、スタッフ同士で私語に夢中になったりしていると、来場者は「話しかけにくい」というバリアを感じ取ってしまいます。
背筋を伸ばして堂々と立ち、通路を歩く来場者と目が合ったら軽く会釈するなど、常にオープンで歓迎する姿勢を心がけてください。
リラックスした自然な笑顔は、相手の警戒心を解き、円滑なコミュニケーションのきっかけを作る最も効果的なツールです。
正しい名刺交換のやり方を覚えよう

名刺交換には一連の決まった流れ(やり方)があります。
この手順、いわば「型」を身体で覚えておくだけで、どんな場面でも慌てることなく、相手に丁寧で洗練された印象を与えられます。
特に展示会のように、多くの人と短時間で立て続けに交換する場面では、スムーズな所作が求められます。
1. 差し出す側(目下・訪問者から)
名刺交換は、基本的に立場が下の人や、訪問した側から先に差し出すのがビジネスマナーの基本です。
ブースの出展者は来場者を「迎える」側ですが、来場者は「お客様」であるため、出展者側から自発的に動く姿勢が好印象につながります。
名刺は名刺入れから取り出し、両手で胸の高さに持ち、相手が文字を読みやすい向きにして差し出します。
その際、「株式会社〇〇、営業部の△△と申します。本日は弊社ブースにお立ち寄りいただきありがとうございます。」のように、会社名、部署名、氏名をはっきりと、相手の目を見て名乗りましょう。
2. 受け取る側
相手が名刺を差し出したら、こちらも名刺入れを下に添えるようにして、両手で丁寧に受け取ります。
その際は必ず「頂戴いたします。」と一言添えるのが基本です。受け取った名刺にはすぐに目を通し、「〇〇様でいらっしゃいますね。」と相手の名前を復唱することで、名前を確実にインプットすると同時に、相手への敬意を示すことができます。
もし名前が読みにくい場合は、「失礼ですが、何とお読みすればよろしいでしょうか?」と素直に尋ねましょう。
3. 同時交換の場合
展示会の現場では、お互いがほぼ同時に名刺を差し出す「同時交換」の場面が頻繁に発生します。
この場合は、右手で自分の名刺を差し出し、同時に相手の名刺を左手で受け取ります。受け取った後はすぐに右手を添えて、両手で持つようにしましょう。
この一連の動作をスムーズに行えるよう、事前に練習しておくと安心です。
受け取った名刺の扱い方
受け取った名刺をすぐにしまうのは、「あなたに興味がありません」という無言のメッセージと受け取られかねない、重大なマナー違反です。
商談スペースのテーブルに着席した場合は、相手の座席順に合わせてテーブルの上に並べます(最も役職の高い人を自分の左側に配置するのが基本)。
立ち話の場合は、会話が終わるまで名刺入れの上に一時的に保持し、丁寧に扱います。
名刺を渡す時、なんて言えばいいですか?

名刺交換の際に添える一言は、単なる挨拶を超えて、その後の会話のきっかけを作り、相手の記憶に残るための重要なフックとなります。
型通りの挨拶だけでなく、その場の状況や相手の関心に応じた言葉を瞬時に加えることで、その他大勢との差別化を図ることができます。
「渡す時、なんて言えばいいですか?」という具体的なフレーズに不安を感じる方は、以下のテーブルを参考に、いくつかのパターンを頭に入れておくと良いでしょう。
| シチュエーション | 声かけの例 | ポイントと応用 |
|---|---|---|
| 基本的な声かけ | 「はじめまして。株式会社〇〇の△△と申します。よろしくお願いいたします。」 | 基本中の基本です。はっきりとした声と笑顔、そして丁寧なお辞儀をセットで行うことが重要です。 |
| 相手が製品に興味を示した時 | 「ご興味を持っていただきありがとうございます。詳しい資料もございますので、よろしければお名刺を交換させていただけますでしょうか。」 | 相手の「知りたい」という気持ちを尊重し、次の情報提供につなげる自然な流れを作れます。 |
| こちらからアプローチする時 | 「御社の〇〇の取り組みについて、以前からメディアで拝見しておりました。ぜひ一度、情報交換させていただきたく存じます。」 | 相手企業について事前にリサーチしていることを示すことで、単なる数合わせではない、本気度の高いアプローチであることを伝えられます。 |
| セミナーやデモ直後 | 「先ほどのセミナー、〇〇という点が特に興味深く、大変勉強になりました。よろしければ、お名刺交換をお願いできますでしょうか。」 | 共通の体験を話題にすることで、共感が生まれ、会話が弾みやすくなります。具体的な感想を述べることがポイントです。 |
最も大切なのは、相手との共通点や接点を見つけ、それを言葉にして伝えることです。
相手がブースのどのパネルに注目していたか、どんな質問をしたか、あるいは相手の名刺に書かれた役職や所在地など、あらゆる情報が会話の糸口になります。
観察力を働かせ、パーソナライズされたコミュニケーションを心がけましょう。
準備すべき名刺の枚数の目安は?
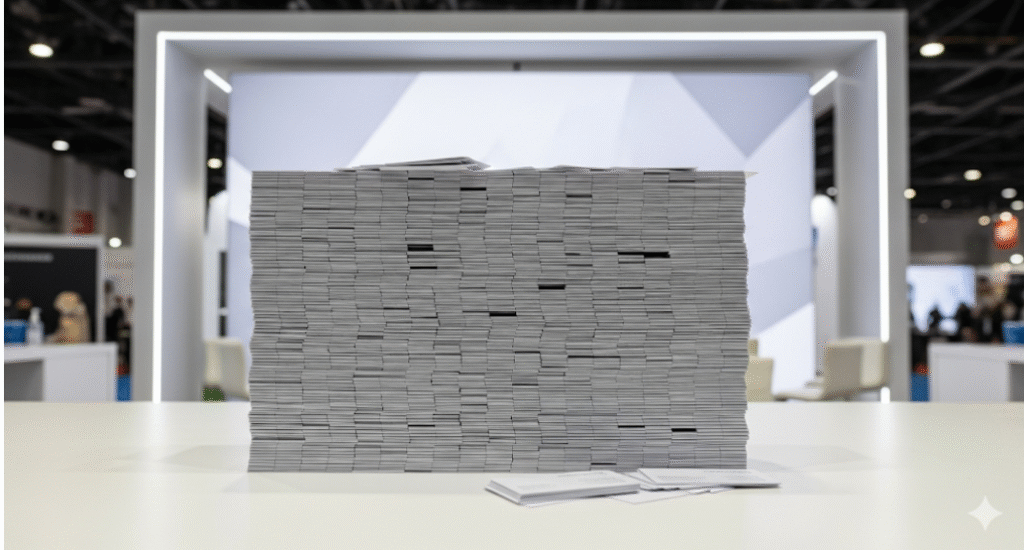
展示会において、名刺切れは成約機会を丸ごと失うことに等しい、最大の機会損失の一つです。
「どれくらいの枚数を交換するか見当がつかない」という場合でも、常に「多すぎるかもしれない」と感じるくらい準備するのが鉄則です。
必要な枚数は、展示会の規模、会期、ブースの立地条件、担当者の役割によって大きく変動します。
具体的な目安として、中小規模の展示会であっても、出展者側の担当者であれば1日に最低100枚程度は携帯しておくと安心できます。
人通りの多いメイン通路に面したブースや、注目度の高い製品を展示している場合は、1日で200枚以上交換するケースも決して珍しくありません。
戦略的な名刺枚数の準備方法
- 想定交換枚数の算出: 過去の同様の展示会での実績データがあれば、それが最も信頼できる指標です。なければ、展示会公式サイトに掲載されている前回の来場者数や出展社数を参考に、自社ブースへの想定来訪者数と名刺交換率(例:来訪者の30%)を設定し、おおよその枚数を予測します。
- 潤沢な予備の確保: 算出した予測枚数に加えて、最低でも20~30%の予備を用意しておきましょう。予備はブース内の施錠できるストック場所に保管し、携帯する名刺入れの中身が少なくなったらすぐに補充できる体制を整えておくことが重要です。
- チーム全体でのリソース共有: 担当者が複数いる場合は、全員が十分な量を持っていることを朝礼などで確認します。特定の人気スタッフに名刺交換が集中することも考慮し、チーム内で名刺を融通し合えるようにしておくなど、組織的な対応が求められます。
展示会に名刺をいくつ持っていけばいいですか?
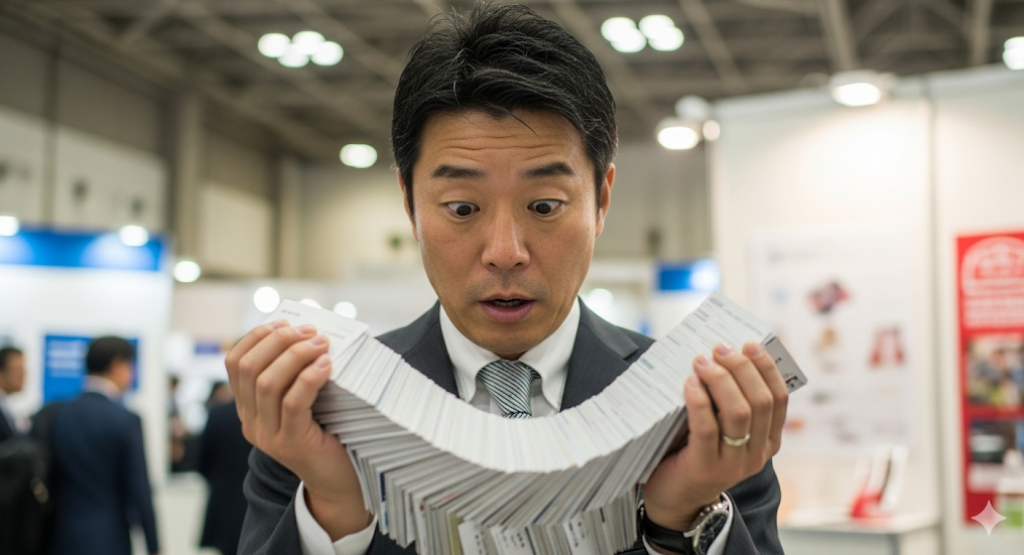
前述の通り、準備すべき名刺の枚数は多ければ多いほど安心ですが、「展示会に名刺をいくつ持っていけばいいですか?」という具体的な疑問に対しては、参加する立場(出展者か来場者か)によって適切な回答が大きく異なります。
出展者側の場合
出展者としてブースに立ち、見込み顧客を獲得することがミッションである場合、名刺交換は業務の核心部分を占めます。
3日間の会期であれば、少なくとも300枚~500枚は準備しておくべきでしょう。
特に、最前線で来場者対応を行う営業担当者や、最終的な商談のキーマンとなる可能性のある役職者は、積極的に交換を行うため、より多くの枚数が必要です。
名刺切れを起こして「申し訳ございません、切らしておりまして…」と謝罪する事態は、企業の準備不足を露呈し、大きなイメージダウンにつながることを肝に銘じる必要があります。
来場者側の場合
一方、来場者として特定の業界の動向調査や情報収集、既存の取引先への挨拶回りなどを目的に参加する場合は、出展者側ほど大量の枚数は必要ありません。
ただし、様々なブースで積極的に説明を聞き、新たなサプライヤーやパートナーを見つけたいと考えている場合は、1日の訪問で最低でも50枚程度は持っておくと安心です。
Sansanのような名刺管理アプリの普及により、近年ではQRコードを用いたデジタル名刺交換も増えています。こうしたツールを併用することも、スマートな情報交換の一つの方法です。(参照:Sansan株式会社公式サイト)
来場者側の注意点と心構え
目的もなく名刺を配り歩くのは非効率ですが、興味を持ったブースで詳しい説明を受ける際や、有益な情報を得て今後のコンタクトを取りたいと感じた際には、必ず名刺交換を求められます。
常に名刺入れを携帯し、いざという時にすぐ対応できるよう準備しておくことが、チャンスを逃さないための最低限のマナーです。
展示会 名刺交換を成功させる実践テクニック

- 交換を切り出すベストなタイミングは?
- これだけは避けたいNGな行為は?
- 名刺を渡したくない時のスマートな断り方
- 怪しいと感じる相手やしつこい営業の対処法
- 交換後のフォローメールで差をつける
- 成果につなげる展示会 名刺交換のコツ
交換を切り出すベストなタイミングは?

展示会で効率よく質の高い名刺交換を行うには、適切なタイミングを見極める「間合い」の感覚が極めて重要です。
やみくもに声をかけて名刺を差し出しても、相手に警戒されたり、冷たく断られたりする可能性が高く、精神的にも消耗してしまいます。「
タイミングは?」と迷った時は、相手の行動、視線、そして会話の中身から関心の度合いを正確に読み取りましょう。
結論から言えば、最も効果的なタイミングは、相手が自社の商品やサービスに対して、具体的な興味や関心を示した瞬間です。この「ゴールデンタイム」を見逃さない観察力が、成果を大きく左右します。
1. 相手から具体的な質問が出た時
来場者がブースに立ち止まり、展示パネルを熱心に読んだ後、「この製品の価格帯はどのくらいですか?」「〇〇という課題にも対応できますか?」といった具体的な質問をしてきた時は、絶好のチャンスです。
これは、相手が単なる情報収集から一歩踏み込み、自社の状況と照らし合わせ始めたサインです。「詳しいご説明の前に、よろしければお名刺を頂戴できますでしょうか?」と切り出すことで、非常にスムーズに交換できます。
相手はすでに前のめりで情報を求めているため、拒否される可能性は極めて低いでしょう。
2. 会話が盛り上がり、共感ポイントが見つかった時
製品説明やデモンストレーションを通じて会話が弾み、「まさに、そういう機能を探していたんです」「弊社の課題はまさにそこなんです」といった、相手の抱える課題と自社のソリューションが明確に一致したと感じた時も、絶好のタイミングです。
「ぜひ今後も継続的に情報交換させていただきたく存じます。差し支えなければ、お名刺を交換させていただけますか?」と提案することで、単なる製品情報の交換以上の、長期的なパートナーシップ構築への意欲を示すことができます。
3. 資料やノベルティを渡す時
来場者がカタログや技術資料、あるいは魅力的なノベルティを受け取った瞬間も、心理的な「返報性の原理」が働き、自然な流れで名刺交換に移行しやすいタイミングです。
「こちらの資料と併せて、私の名刺もお渡しさせていただきます。何かご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。」と切り出し、自然に交換を促しましょう。
絶対に避けるべきタイミング
ブースの前を足早に通り過ぎようとしているだけの人や、手元のマップを見ながら明らかに他のブースを探している様子の人に、通路に立ちはだかるようにして名刺交換を迫るのは最悪のタイミングです。
相手に強い警戒心と不快感を与え、企業イメージを損なうだけの逆効果になる可能性が高いです。
これだけは避けたいNGな行為は?

良かれと思って取った行動や、無意識の癖が、実は重大なマナー違反だったというケースは少なくありません。一度与えてしまった悪い印象を覆すのは困難です。
展示会での企業の評判を守り、将来のビジネスチャンスを潰さないために、以下のNGな行為は絶対に避けましょう。
1. 受け取った名刺をすぐにしまう
これは最も頻繁に見受けられる、そして最も相手を不快にさせるNG行為の一つです。
受け取った名刺に一瞥もくれずに名刺入れやポケットにしまう行為は、相手に対して「あなたという個人にも、あなたの会社にも興味がありません」という無言のメッセージを送っているのと同じです。
必ず受け取ったら一読し、相手の氏名、役職、会社名を確認する時間を取りましょう。
2. 相手の前で名刺にメモを取る
名刺は相手の「顔」とも言える大切なものです。相手が見ている前で、その「顔」に堂々とボールペンで書き込みをするのは非常に失礼にあたります。
後で思い出すためのメモは重要ですが、取る場合は必ず相手と別れた後、ブースのバックヤードなど見えない場所で行うのが鉄則です。
どうしてもその場でメモが必要な場合は、「大変失礼ですが、〇〇の件、忘れないように少しメモさせていただいてもよろしいでしょうか?」と一言、丁寧に許可を得る配慮が必要です。
3. 名刺切れを起こす
これは準備不足の象徴であり、プロフェッショナルとして失格の烙印を押されかねない行為です。
「申し訳ございません、名刺を切らしておりまして…」という言葉は、ビジネスチャンスを自ら手放すだけでなく、企業の管理体制の甘さを露呈する行為にほかなりません。
出展者としては致命的なミスと認識し、これでもかというほどの枚数を準備しておく必要があります。
4. 一方的な売り込みに終始する
名刺交換をすることがゴールであるかのように、相手の話を遮ってまで自社の製品やサービスの説明だけを一方的に、かつ早口でまくし立てるのは最悪のコミュニケーションです。
展示会は対話の場であり、まずは「御社ではどのような課題をお持ちですか?」といった質問を通じて、相手の状況やニーズを丁寧にヒアリングする姿勢が何よりも重要です。
目的は「名刺の枚数を集めること」ではなく、「信頼関係の第一歩を築くこと」であると、常に意識しましょう。
名刺を渡したくない時のスマートな断り方

展示会では、自社の事業領域とは全く異なる業種の人や、明らかに個人的な人脈作りや営業目的のみで手当たり次第に声をかけてくる人から、名刺交換を求められることも少なくありません。
貴重な情報を渡したくない、あるいは無駄な営業を受けたくないと感じた場合、無下に断ると角が立ち、思わぬところで悪い評判につながる可能性もあります。
ここでは、相手の気分を害さず、かつ自社の立場を守るスマートな断り方を紹介します。
断り方の基本方針:「相手を否定せず、こちらの都合やルールを理由に、丁寧にお断りする」
1. 在庫切れを理由にする(来場者向け)
最も一般的で角が立たない、便利な断り方です。
特に来場者として参加している場合に有効です。
フレーズ例:「大変申し訳ございません。あいにく想定以上に多くの方と交換しまして、ちょうど名刺を切らしてしまいました。」
このフレーズに、少し申し訳なさそうな表情を加えることで、相手もそれ以上強くは要求しにくくなります。
ただし、出展者側がこの理由を多用すると、前述の通り準備不足を疑われるため、使いどころには注意が必要です。
2. 立場や目的を理由にする
自身の役割や当日の目的を明確に伝えることで、交換に応じられない正当な理由を示す方法です。
フレーズ例:「お声がけいただきありがとうございます。ただ、本日はあくまで情報収集(あるいは技術的な視察)を目的としておりますので、大変恐縮ながら名刺交換は一律で控えさせていただいております。」
「一律で」という言葉を加えることで、「あなただから断る」のではなく、個人的なルールであることを示唆し、相手の自尊心を傷つけにくくする効果があります。
3. 資料のみ受け取る姿勢を示す
相手が製品カタログなどを渡そうとしてきた流れで名刺交換を求められた場合は、情報提供への感謝を示しつつ、交換は次のステップであることを示唆します。
フレーズ例:「ありがとうございます。まずはいただいた資料を社内に持ち帰り、じっくりと検討させていただきます。」
この際、相手の名刺だけを受け取り、自分の名刺は渡さないという非対称な対応は、相手によっては不快感を持つ場合もあるため、慎重に行うべきです。
怪しいと感じる相手やしつこい営業の対処法

多くのビジネスパーソンが集まる展示会には、残念ながら本来の目的とは異なる、質の低い営業や勧誘活動を行う人々も紛れ込んでいます。
自社のサービスとは全く関係のない投資話や、過度に高額なコンサルティング契約をしつこく勧めてくる営業担当者に遭遇することもあります。
貴重な時間を奪われ、不快な思いをしないために、怪しいと感じた場合の対処法を知っておくことは非常に重要です。
1. 曖昧な態度は取らず、早めに、しかし丁寧に話を切り上げる
興味がないにもかかわらず、相手に失礼かもしれないと愛想笑いで話を聞き続けてしまうと、相手に「この人は話を聞いてくれる」「脈ありかもしれない」と誤解させ、さらにしつこい営業を招く最悪の結果につながります。
興味がない、必要ないと感じた場合は、会話の早い段階でその旨を明確に、しかし丁寧な言葉で伝えましょう。
フレーズ例:「大変申し訳ありませんが、弊社の事業とは直接的な関連性が薄いようですので、今回は見送らせていただきます。貴重なお話をありがとうございました。」
2. 時間を理由に物理的に離脱する
話が長引きそうな場合や、相手が引き下がらない場合は、次の予定があることを理由に会話を強制的に打ち切るのも有効な手段です。
フレーズ例:「大変申し訳ありません、次のアポイントの時間が迫っておりますので、この辺で失礼させていただきます。」
そう言って軽く会釈し、物理的にその場を離れることで、相手もそれ以上追ってくることは難しくなります。これは最終手段ですが、非常に効果的です。
悪質な勧誘には注意を
万が一、脅迫的な言動やあまりに執拗な勧誘を受けた場合は、個人で対応しようとせず、速やかに展示会の運営事務局や警備員に報告しましょう。
トラブルを未然に防ぐためにも、毅然とした態度が求められます。(参考:国民生活センター「各地の消費生活センター」)
展示会では、新しいビジネスチャンスを探すと同時に、自分の時間と会社の情報を守るという危機管理意識も大切です。全ての要求に応じる必要は全くありません。
自社の利益にならない、あるいはリスクがあると判断した場合は、丁寧にかつ毅然とお断りする勇気を持ちましょう。
交換後のフォローメールで差をつける
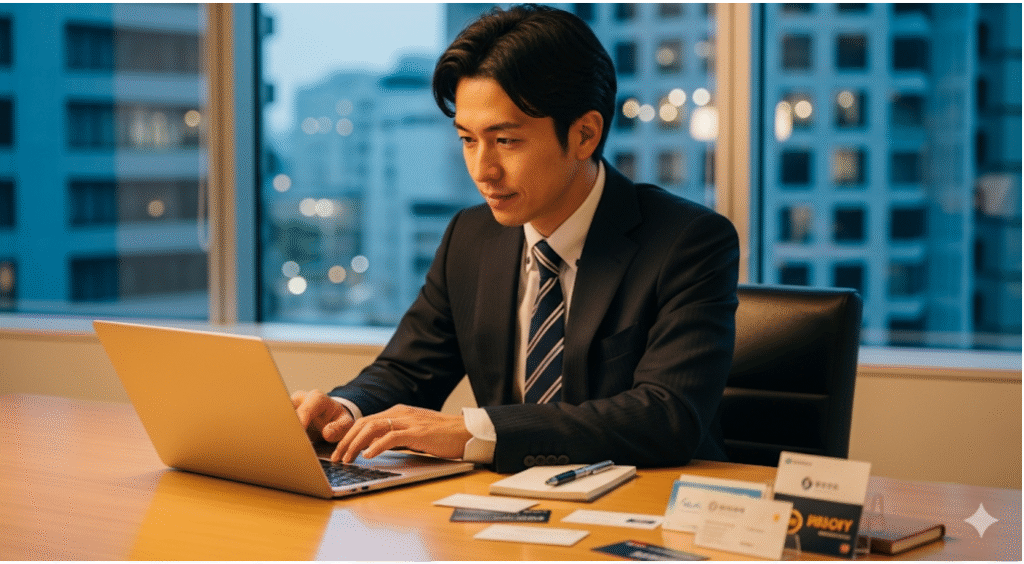
展示会で名刺交換しただけで満足してしまうのは、あまりにもったいないことです。
本当の勝負は、熱気の冷めやらぬ展示会終了後に始まります。
交換した貴重な名刺を単なる紙切れで終わらせるか、未来の優良顧客へと育てるかは、迅速かつ効果的なフォローアップにかかっています。
1. フォローメールの重要性とタイミング
展示会の来場者は、数日間のうちに何十、何百というブースを回り、大量の名刺を交換しています。
時間が経てば経つほど、自社ブースで交わした会話や製品の記憶は薄れてしまいます。そのため、フォローメールは遅くとも展示会終了後の翌営業日中に送信するのが鉄則です。
可能であれば、会期中であってもその日の夕方や夜に送ることで、他社に圧倒的な差をつけ、強い印象を残すことができます。
2. 成果につながる効果的なメール文面の構成
名刺管理ソフトから一斉送信された、誰にでも当てはまる定型文メールは、開封すらされずに迷惑メールフォルダ行きになる可能性が高いです。
手間はかかりますが、相手の記憶を呼び覚まし、「自分のために送ってくれた」と感じさせる工夫を凝らすことが、返信率を高める鍵となります。
記憶に残るフォローメールの構成要素
- 一目でわかる件名: 例:「【〇〇展示会】〇〇の件でのご来場の御礼(株式会社自社名・担当者名)」のように、【展示会名】と具体的な会話のキーワードを入れることで、開封率が格段に上がります。
- パーソナライズされた本文: 「当日は、貴社の〇〇という課題について、熱心にお話しいただき、誠にありがとうございました。」のように、具体的な会話内容を一言でも盛り込むだけで、その他大勢向けのメールではない、特別な一通であるという印象を与えられます。
- 明確な次のアクション提示(Call to Action): メールを送る目的(資料送付、オンラインでの商品説明、アポイント打診など)を明確に記載します。「つきましては、お話にあがりました〇〇の詳しい導入事例を、来週あたり15分ほどオンラインでご紹介するお時間を頂戴できますと幸いです。」など、相手が「はい/いいえ」で答えやすい具体的な提案を行いましょう。
戦略的な名刺管理と優先順位付け
交換した全ての名刺に同じ熱量でアプローチするのは非効率です。
会話の内容や相手の関心度、役職などから、「Aランク:3営業日以内に電話でアポイント打診」「Bランク:1週間以内にパーソナライズドメールでフォロー」「Cランク:一斉メールで定期的な情報提供」のように、獲得したリードをセグメント分けし、それぞれに最適なアプローチを行う体制を事前に整えておくことが、展示会の成果を最大化する上で極めて重要です。
成果につなげる展示会 名刺交換のコツ
最後に、展示会での名刺交換を単なる挨拶や儀礼で終わらせず、具体的なビジネス成果、すなわち売上向上につなげるための要点を総括します。
以下のポイントをチーム全員で共有し、戦略的に展示会に臨みましょう。
- 展示会での名刺交換は「質の高い見込み顧客リストを獲得する」という明確な目的意識を持つ
- 企業の顔として、清潔感のある身だしなみと、歓迎の意を示すオープンな立ち振る舞いを徹底する
- 名刺交換の基本的なマナー(渡し方、受け取り方、扱い方)を身体で覚え、スムーズな所作を心がける
- 名刺は常に想定の1.5倍以上を準備し、名刺切れという致命的なミスを絶対に起こさない
- 相手の課題やニーズを巧みに引き出すヒアリング力を最優先し、一方的な製品説明や売り込みは厳に慎む
- 交換した名刺の余白や裏面には、相手の外見的特徴や会話のキーワードをその場ですぐにメモし、記憶を補強する
- 同時交換の場合は「右手で渡し、左手で受け取る」という原則を徹底する
- 受け取った名刺はすぐにしまわず、必ず記載内容に目を通し、相手の名前を復唱する
- 名刺交換を断られた場合でも感情的にならず、「ご縁がなかった」と割り切り、次の機会に集中する
- 展示会終了後は、記憶が鮮明なうちに、可能な限り早く(理想は24時間以内に)フォローアップを開始する
- フォローメールには定型文だけでなく、必ず個別の会話内容を反映させ、パーソナライズすることで他社と差別化する
- 獲得した名刺情報(見込み度、課題、役職)に基づきリードをランク付けし、アプローチの優先順位と方法を最適化する
- すぐに商談化しないBランク以下の相手でも、見込み客として育成する(リードナーチャリング)という中長期的な視点を持つ
- 怪しいと感じる相手や、目的が明らかに異なる営業には、丁寧かつ毅然とした態度で断る勇気を持つ
- 最終的なゴールは名刺の枚数ではなく、その後の商談や受注につながった件数であることを常に意識する




コメント